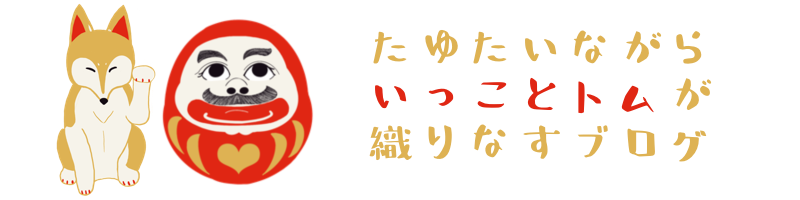去年の7月に夫のケアプランを見直し、通所施設を、認知症対応型デイサービスからデイケアに変更しました。
それによる1番の変化が、夫の皮下出血が劇的に減ったことでした。
その要因として考えられるのが、あくまで私の推測ですが、設備の違いと介護における重点、そして職員教育の差です。
認知症対応型デイサービスは、一般的な民家をデイサービス向けに改装した施設で、外観・内装ともにほぼ民家。事業はデイサービス1ヶ所だけ。家族経営に近い小規模法人。
一方、デイケアは、介護老人保健施設(老健)が併設され、同じ建物内には、特別養護老人ホーム(特養)とデイサービスも併設されている。社会福祉法人運営。
【設備の違いについて】
認知症対応型デイサービスの建物と設備
玄関ポーチに段差があり、さらに玄関ホールにも上り框がある。
見学にいったときに見ただけなので、はっきりと記憶にないが、浴室は家庭用の浴槽を使った個浴で、手すりやチェアなどの福祉用具が設置されている程度。トイレは、少し広めの家庭用トイレに手すりがついている。送迎車は、福祉車両でなく乗用車。
デイケアの建物と設備
利用者さんが活動する範囲は、ほぼバリアフリーと思われる。
浴室は、大きな浴槽とは別に、チェア型の特殊浴槽がある(夫はこちらを利用)。トイレは見学していないが、おそらく車椅子のまま入室できるように、ある程度の広さが確保されていると思われる。送迎車は、車椅子のまま乗り降りできる福祉車両。
【介護の重点について】
夫は、3ヶ所の認知症対応型デイサービスを利用した経験があり、その経験を通じて私が得た感触としては、認知症対応型デイサービスは、主に本人の意思の尊重に重点が置かれているように感じる。
これは、デイケアが本人の意思を尊重していないという意味ではない。
認知症対応型デイサービスを利用する人の場合、本人の意思を尊重しなければ強い利用拒否につながり、利用自体が困難になってしまう。
一方、デイケアを利用する人は、ある程度のがまんができる。つまり、自分でがまんをある程度コントロールできる。もしくは、認知症があっても、現在の夫のように症状が落ち着いているか。
がまんの限界を迎えたとき、どのように振る舞うか。
そこに認知症対応型デイサービスを利用する人と、デイケアを利用する人の、大きな違いがあるのではないだろうか。
認知症対応型デイサービスとは、利用者さんががまんの限界に達したとき、その人の感情や行動に、どれだけ人員を割き、どこまで試行錯誤して対応にあたれるのか。そこに真価が問われる介護施設である。
さらには、利用者さんが、がまんの限界に達さないよう、利用者さんの心情に寄り添うための人員を割き、臨機応変に対応してくれる。
その点、デイケアは、このような細やかな対応を求める介護施設ではなく、主目的はリハビリである。
もちろん、意思の尊重はしてくれるだろうが、認知症対応型デイサービスとは尊重できる幅と限度が違う。
また、本人の意思を尊重するために、安全がやや犠牲になる可能性を内包しているのが、認知症対応型デイサービスである。
これは、デイケアが安全という意味ではなく、本人の意思の尊重と安全の確保、この両方を完璧に両立させることなど、土台無理な話なのだ。
その土台無理な話を可能な限り遂行しようとしてくれるのが認知症対応型デイサービスであり、可能でも不可能でもとにかく本人の安全を守るために身を粉にしているのが、そばにいる家族である。
【職員教育について】
認知症対応型デイサービスのみを運営する小規模法人と、複数事業を抱える社会福祉法人とでは、職員教育の内容に違いが生じると考えられる。
職員研修にどこまで力を入れるかは経営者の考えに左右されるが、小規模法人だと、職員研修にそこまでお金がかけられないという現実がある。
一概にはいえないが、職員数が多い施設であれば、法人が施設内研修を行なったり、法人負担で職員が外部研修を受ける機会があったりする一方で、小規模な施設では職員が自己負担で外部研修を受けに行く傾向があるようだ。
また、社会福祉法人の場合、利用者家族からの無茶な要望や理不尽な要求に対応してきた経験が豊富にあり、その経験の蓄積によって、皮下出血やケガに対する職員の危機意識の高さや敏感さにつながっているのかもしれない。
もちろん認知症対応型デイサービスも、家族からのそのような要望や要求に対応してきてはいるだろうが、利用者数が違うので、対応してきた数も違ってくる。さらに、分母が大きくなれば、トラブルにつながりやすい家族に対応するケースも必然的に増えるだろう。
そのような家族への対応経験の蓄積が結果として、皮下出血やケガを防ぐための職員教育の徹底や介助技術の向上につながっているのかもしれない。
皮下出血について私の考え
以上が私の考察であり、ここからが本題です。
まず初めに、私は、皮下出血は、どこかに打つけることでできると思っていたのですが、Instagram(@ikotom.23)のストーリーズで質問したところ14名もの方からDMをいただき、皮膚や血管が弱くなると、打たなくても皮下出血するということを教えていただきました。
ちょっと強く圧がかかったとか、寝てるとき背中側に服のシワがあったとかでも皮下出血するそうです。
ですが、ここでは、それなりに活動量がある人が、どこかに打ったりしてできた皮下出血を前提にして書きます。
夫が、認知症対応型デイサービスを利用していた最後の一年くらいは、夫の皮膚にはほぼ常時どこかしらに皮下出血がありました。
気づかないうちにできていることも多いのが皮下出血であり、いつどこでできたのか特定するのが難しいこともありますが、大半の皮下出血が、その認知症対応型デイサービスでできたのだろうということは、夫の前後の状態から推測できました。施設の人が気づいた皮下出血については報告もありましたし。
けれども私は、夫の皮下出血について、そこまで気にしていませんでした。
これは夫が認知症になる前に話してくれたことですが、夫の「父も祖父も皮下出血できやすい体質だった」ようで、「だから自分が皮下出血できるようになったとき歳をとったと感じた」そうです。
そう、夫は、認知症になる前から、たびたび皮下出血を自前でこしらえていたのです。なので、夫は皮下出血しやすい体質であり、わりとおっちょこちょいであると、私の中にインプットされていました。
さらに私の信条が「生きてればケガぐらいする。ほっておいても治るケガは、そんなに気にする必要ない」なんです。
なので、夫の皮下出血を見ても「歳をとったら、そんなもんなのかな」くらいの認識でした。
けれども、仕事としてケアに関わっている方々にとって皮下出血は見逃してはならないものであり、夫の皮下出血を発見すると強い反応を示すので、そのようなとき、私はどのような姿勢でいたらいいのか揺れました。
ケア職にとって皮下出血は作ってはダメなものという認識が強いようですが、現実問題、皮下出血を作らない介護というのは夫の現状では無理な話。
複数のサービスを利用し、複数の視点から指摘や提言がある中で、どこで折り合いをつけるのか。夫のキーパーソンである私の悩みどころともいえます。
私は、皮下出血を許容するけれども、どこまで許容していいのかわからない状態。
皮下出血は作らないでほしいけど、注意していても、できてしまうものはしかたがない。
どこまで敏感にならなければいけなくて、どこまで鈍感でいていいのかわからない。
でも、いつも最終的には、「この皮下出血を作ってしまうのは、さすがにまずい、てレベルやったら、きっと訪看さん(訪問看護師)が指摘してくれるはず」と思ってました。
そして一年前、当時の夫の身体状態を鑑みて、近い将来、認知症対応型デイサービスの設備では通所不可能なると判断し、先手を打って現在利用しているデイケアに変更しました。
そしたら、驚くことに、皮下出血が激減したのです。
施設を変更してから1.2ヶ月は、たまたまかもと思っていましたが、もうすぐ1年になるので、たまたまではなさそうです。
夫は皮下出血ができやすい体質だと思っていたけれども、私が思っていたほど、できやすい体質というわけでもなかった。
この1年間、この差がどこから生じているのか観察及び考察した結果、先述した、設備の違い、介護の重点、職員教育、この三要素が思い浮かびました。
もちろんこれは簡略化された答えなので、そんな単純な話ではないと思いますが、私の率直な感想としては「細心の注意と適切な設備があれば、皮下出血はある程度、防げるんやな」です。
私は、皮下出血を、施設が夫の体を動かしてくれた証だと思っています。(実際は、動かなくても皮下出血することはあるようですが)
動くからケガをする。動かなければケガはしない。
さらに、皮下出血は人と触れ合った痕跡でもあります。
介助の際、介助者の手の圧で皮下出血したのだとすれば、それは人と接触した証。
皮下出血の原因が、すぐさま虐待や乱暴な介護になるわけではない。
その人のためを思ってやったことが、皮下出血の原因になっていることもよくある。
私だって、皮下出血しないに越したことはないと思っている。けれども、皮下出血させないようにするために活動量が落ちるなら、皮下出血もやむなしというスタンス。
今の夫は、栄養状態がよく体力もあるので、皮下出血だけならそこまでのリスクはない。皮下出血した箇所の皮膚が弱くなるので注意は必要だけれども、痛みがあるわけではなさそうだから。
動くことはケガのリスクにつながり、安全は廃用のリスクにつながる。
どちらにもリスクはある。
リスクのない介護なんてない。
私はリスクを引き受ける覚悟で夫の介護をしている。