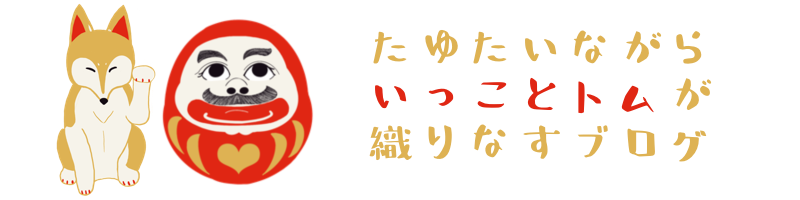私と夫は、一時期、共依存だった。
認知症の症状に起因した不安や不穏が夫に強く出ていたときのこと。
私は、共依存であることを認識し、それを受容していた。
そのときの私にとって共依存の否定は、夫を私から切り離すことであり、ひとりで自問自答できない夫の心を見捨てることを意味した。
これは、周りの人がどんなに否定しても、私にとっては実感を持った事実だ。
家族を捨てるという言葉の意味。
介護している家族と介護をサポートしている人たちとの間には、ズレがあるのだろう。
たとえば、入所施設に家族を託すということ。
いくら、「それは、家族を捨てることではない」と説明されても、家族を捨てるという実感を持つ人もいる。
認知症の症状がある家族を介護しようとすれば、ある程度の共依存は避けられない。
認知症とは、今までの依存先である自分の記憶が揺らぎ、自分の輪郭がぼやける病だからだ。
人間は、積み重ねてきた今までの経験や記憶に依存して、自分の輪郭を認識している。
その自分が揺らぐのだから、他者に依存先を求めるのは、自然なこと。
そして、依存されることになる家族も、多かれ少なかれそれを受け入れる。
なぜなら、相手を受容できない人に、介護はできない。
なぜ、そこから共依存になりやすいのか。
それは、認知症の症状がある人と、そのそばにいる人の関係は、密室になりやすいからだ。
空間としての密室というよりも、心の密室。
言葉にならない感情を行動から読み取ろうとする。
その繰り返し。
「誰よりもこの人のことがわかるのは、私」
おそらく、共依存していればしているほど、捨てるという実感が強くなる。
相手にとって誰よりもわかってくれる存在である自分を切り離す。
誰よりもわかろうとした相手を自ら切り離す。
捨てるという感覚がなければ切り離せないほどのつながりが、そこにはあるのかもしれない。
介護殺人
捨てられなかったから
殺したのかもしれない
私は常々、
死にたいという気持ちが尊重されれば、死ななかった命があると思っている。
もしかしたら、
他人を頼ることは、逃げじゃない、捨てることじゃない。
ではなく、
逃げてもいい、捨ててもいい、逃げて捨てることで守られる命がある。
そう言ってくれる人がいれば、助かった命があったのかもしれない。
そして、私のメタ認知を育てたのは、夫の症状だった。
共依存の中で私は、自分の感情と私の中に入り込んでくる夫の感情を感じわけようとしていた。