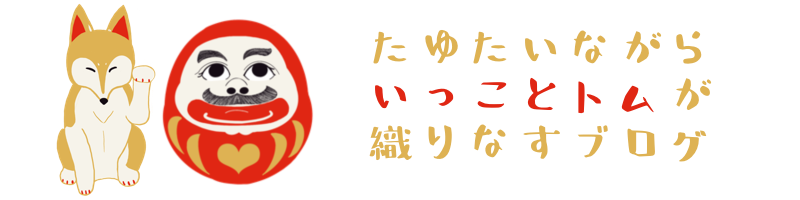認知症のある人に限らず、高齢になると過去の事は思い出せるのに、最近の事は思い出しにくくなっていく。
なぜそうなるのか簡単に説明すると。
過去の思い出は、その人の人生のなかで何度も記憶から引き出され、その都度、思い出として整理され、再び記憶に定着される。
この繰り返しによって過去の思い出は、思い出しやすい記憶の形式、思い出しやすい場所に記憶されることになる。これが、いわゆる長期記憶のメカニズム。
脳の中では、思い出す行為自体が記憶を強化する「思い出すほど、思い出しやすくなる」という仕組みになっていて、だから過去の思い出深い事柄は、思い出しやすい。
また、一見、過去の同じ出来事を思い出しているようで、脳の中では、当時の記憶そのままではなく、思い出しと定着の反復によって再構築された記憶が引き出されており、再構築の過程で、思い違いや思い出補正が常に起こっている。
最近の事が思い出しにくくなるのは、記憶を脳に定着させる機能が低下しており、脳への書き込みがうまくできなくなるから。
思い出せないというよりも、そもそも思い出せるような形式で覚えていないのだ。
さらに、長期記憶にあるはずの過去の記憶が思い出しにくくなるのは、記憶を引き出すための機能が低下していくから。
新しいことを覚えられない。
昔のことも思い出しにくくなっていく。
そんな中で、思い出すことができる長期記憶は、自分の記憶があやふやになっていく人にとって、宝物かもしれない。
何度も繰り返し話される昔の話は、その人にとって自分自身を保つ軸なのだろう。
私は、認知症という病を、あやふやを調整する能力が低下していく病だととらえている。
私たちの周りには、あやふやなもので溢れていて、あやふやさを整合性があるかのように捉えられる能力が人間には備わっている。
例えば「20年前の思い出」といったとき。その「20年前」という感覚は、時計やカレンダーから得られる客観的な数字ではなく、「その思い出に紐づいた記憶」を頭の中で手繰りよせることで、まかなわれている。
「20年前の思い出」の周辺にある記憶の集合によって「20年前」という感覚が浮かび上がるのだ。
記憶の中に収まっている過去や時間とは、実にあやふやなものだ。
思い出と結びついていた記憶の紐が切れたとき、それがいったいいつの記憶なのか、わからなくなる。
そして、その紐が切れていくのが認知症という病の一側面でもあるだろう。
思い出は、過去の時間と深く結びついている。
子どもの頃の思い出。
子どもから大人になっていく頃の思い出。
大人になってからの思い出。
いま自分が思い出している記憶が、いつ頃の自分の記憶かわからず、40年前の自分が、今の自分のように感じられる。
認知症とは、今の自分と過去の自分との関係があやふやになる病ともいえる。
けれども、その40年前の自分が、真に40年前の記憶のみから生まれているかといえば、そうではない。
先ほど述べたように、記憶というのは思い出すたびに再構築され書き換えられている。
思い出補正。
そこにいるのは、昔なりたかった自分の姿かもしれないし、戻りたい昔の自分の姿かもしれない。
夫の脳が夫に見せている夫。それが夫にとっての夫の世界なのだ。
「脳が見せる自分の世界」と「現実に今の自分が暮らしている世界」。
それらは同じ世界のはず。なぜなら、今までがそうだったから。
脳が見せる世界を疑うことは、簡単にできることではない。
認知症という病は、記憶するという行為そのものを忘れるのではなく、脳の機能低下により記憶することがうまくできず、結果的に記憶できない状態になる。
記憶しようとする意欲は残り続けているからこそ、同じ質問を繰り返したり、同じメモを取ったりするのだ。
認知症によって脳に新しい記憶が定着しづらくなると、新しい記憶は常にぼんやりとしたものになる。
一方で、古い記憶はわりと鮮明に思い出せることもあるが、その記憶がいつのものなのか、時間や過去との結びつきは弱くなっていく。
ぼんやりとした新しい記憶と、いつの記憶かわからない鮮明な記憶。
現在と過去の記憶がごっちゃになって新旧の区別がつかなくなる。
夫の記憶は、私の記憶のように時系列に囚われず、過去が現在と同じような時間軸で夫の中に蘇る。
さらに私は、固定概念に縛られているが故に、通常なら起こり得ないような事柄を続け様に易々と思い浮かべることはできない。
けれども夫は、世界のあらゆる法則を無視することができるので、私には理解できない世界観を構築できる。
「認知症によって起きた出来事はすぐに忘れても、感情は残る」といわれていが、そうであっても、私たちの感情よりは、やっぱり忘れっぽい。
「なにが楽しかったのか」その出来事を忘れてしまうので、楽しかった出来事を思い出すことで、そのときの気持ちを再体験することができず、楽しい気持ちも徐々に薄れていく。
さっきまで怒って私に暴言を吐いていたのに、そのことをすっかり忘れて、何食わぬ顔でご飯の催促をしてくる夫。
こっちはまだ、怒りで燃えたぎっているのに。
私は、怒りの原因になった出来事を反芻することで、怒りを持続しているのだ。
夫の記憶は、私の記憶よりも更新速度が速く、私は全くついていけない。
夫の脳は記憶しようとしているが、新しい記憶の定着が弱いので、出来事に対する余韻のようなものがない。
例えば、食後すぐに「ご飯、まだ?」と尋ねる。
食べたこと自体は忘れていても、「ご飯を食べる」という直近の行為や状況は、なんとなく記憶に残っていて、「ご飯、まだ?」と聞いてくるのだろう。
満腹感の感覚が鈍くなっているのもあるだろうが、そもそも「満腹感があれば、ご飯は食べなくていい」という発想にならないのかもしれない。
トイレに行った直後に、再びトイレに行く。
この行為も「行った」と記憶した直後に「行ったっけ?」という記憶が上書きされているのではないだろうか。
記憶が更新されないから繰り返されるのではなく、記憶の定着が不安定で、なおかつ記憶の更新速度が速すぎるため、余韻を感じられず、同じ行為が繰り返し想起されたり、満足感や納得感が定着せずに流れていくため、同じような気持ちが何度も沸き起こってくるのかもしれない。
人間の記憶は、あやふやなものなのだ。
夫の記憶のあやふやさに触れることによって、私は、人間の記憶のあやふやさ、ひいては、そのあやふやさから生まれる可笑しみに目を向ける機会を得た。